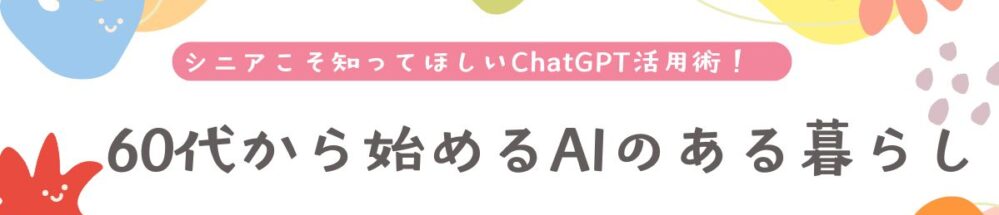おっちゃんが、今日も喫茶店の隅っこで、スポーツ新聞を読みながらコーヒー飲んでたら、またタケルが近づいて来た
おっちゃん、SEOって何なんか教えて
おっちゃんは、読んでいたスポーツ新聞をしまうと、コーヒーをゆっくり飲んだ後、「毎回毎回、タケルにブログについて教えるの疲れたわ」
そんなこと言わんと教えてーな。コーヒーおかわり無料にするから
ほな、しゃーない。
今日はSEOについて、おっちゃんがちゃんと説明したるわ。
目次
検索エンジン最適化
SEOちゅうのは、検索エンジン最適化いうやつや。
ようするにな、SEOというのは、Googleに好かれるように記事を整えるっちゅう話や。
ブログを書くことは、検索エンジンの上位に出るってのが、アクセスを集めるカギなんや。
そのために、読者とGoogleの両方にええ記事やなと思ってもらえるように整える技がSEOということや。
SEOで大事なポイントは4つだけ
- キーワードをちゃんと入れること
- 読者が検索しそうな言葉をタイトルや見出しに入れる(例:「60代の節約術」「初心者のブログの始め方」)
- 見出しを使って構成を整理すること
- H2やH3を活用して、記事にリズムをつけるんや
- 文章をシンプルで分かりやすく書くこと
- 難しい言い回しは避けて、スラスラ読める文にするんやで
- スマホでも読みやすいレイアウトにすること
- 今はスマホで読む人が多いから、文字の大きさや行間にも気ぃつかわなあかん
文字が小さかったり、行間が細か過ぎたら読みにくいやろ。
スマホでパッと読めて、スッと頭に入る構成が大事なんや。
それに、 記事が定期的に更新されてることも大事で、古いまんまの記事は、どんなにええこと書いてても評価が下がることがある。
たとえば、「2019年のおすすめアプリ」なんて、今はもう使われないかもしれへんやろ。
せやから、たまには記事を見直して、情報を新しくすることも大切や。
検索上位に載るには、Googleにこのブログ、読者のために一生懸命書いとると思わせることが必要で、そしたら自然と順位も上がるし読者も喜ぶ。
Googleに気に入られるってことは、つまり、読者にちゃんと向き合うことなんや。
さらに大事なんは、読者が「読んでよかった」と思える内容になっとるかどうかや。
これを、ユーザー満足度って言うんやけど、読者が最後まで読んでくれたり、滞在時間が長かったりすると、Googleさんは「このブログはええ仕事しとる」と思ってくれる。
このことを、Googleさんはどのようにして判断するかというと、読者の滞在時間と記事を最後まで読み切ったかどうかをデーターで判断して、Googleさんは「お、このブログええやん」って思うわけや。
それに、ブログを読みに来てすぐに他の記事に移ってしまったりしたら、それは、読者が求める記事ではなかったと思われて、低い評価の対象になってしまうんや。
SEO対策について詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください。
SEO対策は目的やなくて手段
せやけどな、タケル。
ここからがおっちゃんがほんまに伝えたいことや。
SEOは「目的」やのうて「手段」や。
ブログっちゅうのはな、楽しんで書くもんや。
書いててワクワクしたり、誰かに伝えたくなったりする、そんな気持ちが一番大事やねん。
SEOのルールにばっかり気を取られ、「このキーワードが入ってへんからあかん」とか、「読者が求めてへんこと書いたらあかん」なんて思い込んでしもたら、書くのがしんどなってまう。
ブログは自分の言葉で、自分の想いを届ける場所や。
せやから、おっちゃんはこう言いたいんや。
SEOの基本は押さえたらええ、でも、それに縛られすぎたらあかん。
読者のことを思いながら、自分の気持ちも大事にする。
それが続けられるのが、面白いブログになるんや。
楽しんで書いた記事は、読んだ人にも伝わる。
それが、ほんまの「読まれるブログ」というこっちゃ。
万人に受けなくても、自分が書いたもんが一人でも受け入れてくれる人がいればそれでばんばんざいや。
それが個性というもんであって、けっして自己満足とは違うで。
SEOだけ狙うと、心が抜けるブログになる
検索で上に出るキーワードはたしかに大事や。
せやけど、それだけを追いすぎると、読者の心に届かへん記事になってまう。
たとえば「節約 主婦 方法 2025」みたいなタイトルは検索には強いかもしれんけど味気ないやろ。
大事なんは、キーワードと気持ちがこもった言葉のバランス。
それが検索にも引っかかって、心にも届くブログや。
大事なのは、キーワードと感情を動かす言葉のバランスってこっちゃ。
山登りとブログは似てる
ブログを書くってのは、山登りみたいなもんや。
登山計画を立てるのは大事なこと。
せやけど、その計画に縛られすぎてしもたら、山道の途中にある絶景や風の気持ちよさに気づかれへんようになる。
たとえば、エベレストに登るプロ登山家やったら、計画通りに頂上を目指すことが最優先や。
でも、のんびりトレッキングを楽しむ人やったら、途中で立ち止まって写真を撮ったり、景色を眺めたりする余裕が山登りの楽しみや。
ブログもそれと同じや。 収益を目的にするなら、SEO計画に忠実に進めることが大事や。
けど、書くことそのものを楽しみたいんやったら、計画はあってもええけど、縛られすぎずに、自分のペースで楽しみながら書くほうがええ。
ペルソナ設定、ジャンルやキーワードの選定 、読みやすい構成、SEO対策にしても、これらは登山装備みたいなもんや。
しっかり準備しながらも、道中の風景を味わえるような登山スタイルと同じように、ブログを書くことも一番続けやすくて読まれるブログにつながる。
書くことは基本をおさえた上で、自分のペースで楽しみながら楽しむことや。
自分らしく書いた記事が一番伝わる
ええか、タケル。
ブログはな、誰かの役に立ったり、共感されたり、背中を押すような記事に育てていくもんや。
SEOを勉強することは悪くない。
けど、それに心を奪われて、自分の気持ちが乗らへんブログになったら、それは読まれるブログやのうて、消えていくブログや。
せやから、こうまとめとくで、SEOの基本は大事や、でも、それは読者に届くための手段であって、一番大事なんは、自分らしく楽しんで書くことということや。
そんなブログやったら、きっと一人でも「読んでよかった」って思う読者に届くはずや。
それが、ほんまに読まれるブログやって、おっちゃんは信じとる。
おっちゃんの物語
タケル、せっかくやから今日は、おっちゃんのこと話すことにする。
実はな、おっちゃん、生まれは東京ということ話したと思うんやけど、若い頃、吉本新喜劇にどっぷりハマってな。
テレビで見ては、「なんやこの世界!最高やん!」って思って、思い切って大阪に出てきたんや。
「ボケとツッコミ」いう文化に、心の底から惹かれてな、いっちょ漫才やってみたろ思うて、相方見つけて舞台にも立ってみた。
けどな、うまくいかへんかった。
なんちゅうかな、生まれた時からボケとツッコミを覚えてる大阪人には、どうしても勝てんかったんや。
たとえばやけど、関西の子は3歳で「なんでやねん」言うてる。
こっちは同じ事言ってるつもりでも、なんかズレててな。
大阪の笑いって、やっぱり空気感と反射神経がものを言う世界やと痛感した。
せやから、夢見た舞台はあきらめた。
でもな、あきらめてよかったとも思ってる。
なんでかって。
今のおっちゃんは、たこ焼き屋として毎日楽しく働いてるんやけど、これが意外と繁盛しててな。
ほんまにありがたいことや。
「なんで東京もんがたこ焼きなんや」って言われることもあるけど、それがええんやと思うてる。
大阪に憧れた東京もんの目線で作るたこ焼きやからこそ、「ちょっとちゃうけど、なんかええなぁ」と思ってもらえるんや。
つまりな、自分にないもんを無理に手に入れようとするより、自分にあるもんで勝負したらええってことや。
大阪人にはできん、大阪のたこ焼き。
それが、東京もんの、おっちゃんにできた、自分らしいたこ焼きなんやと思う。
ブログも同じ
せやからな、タケル。
ブログを書くのも、おっちゃんが大阪で商売始めたことと同じやと思うねん。
最初はな、「ブログはこう書かなあかん」「これが正解や」って思いがちやろ。
でもそれって、みんなが右にならえして書いたら、読者から見たらどれも同じに見える記事になってまう。
おっちゃんも一時期、ブログに興味を持った時は、テクニックばかり気にしていた。
その時、思ったのが、「東京から見た大阪」っていう目線は、おっちゃんにしかないんやって気づいたんや。
SEOや、キーワードやって追いかけるのもええけど、それ以上に大事なんは、自分が見てきた風景や感じたことを自分の言葉で書くことなんやと思う。
人が笑うツボはそれぞれや。
せやけど、人が「共感する」ってのは、その人がほんまに感じてることにしか出会われへんのや。
せやから、たとえ誰かが「そんなの意味あるん」って言うても、自分の経験や気づきを、素直に書いた記事こそ誰かの心にちゃんと届いている。
おっちゃんがたこ焼きで成功できたんは、「大阪を目指す東京人」という自分らしさをあきらめずに、表現の形を変えて続けたからやと思うねん。
ブログもそうやで。
向いてる方法が見つからへんのなら、形を変えてみたらええ。
他の人には書けへん、自分にしか見えへん風景を言葉にすることが、誰かの心にちゃんと届くええブログになるんや。
どうや、タケル。
おっちゃん、なんかええこと言うた気ぃせぇへんか(笑)
次回は、「自分にしか書けへんブログって、どうやって見つけたらええんやろ」ということについて、またタケルとおっちゃんが語り合う予定です。
【登場人物が分からない方はこちら】→ 大阪のおっちゃんと仲間たち