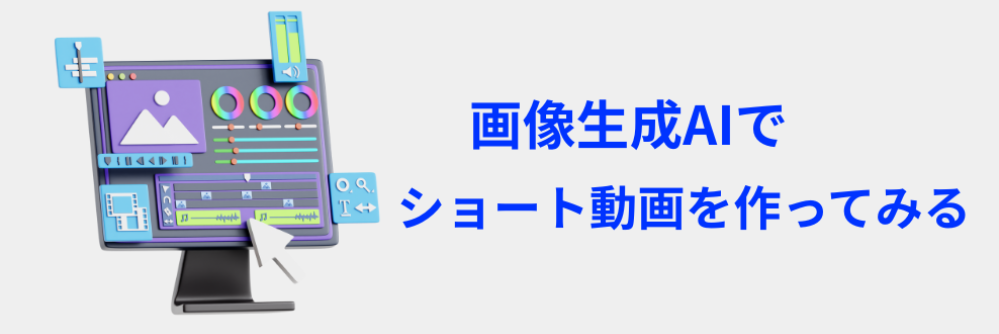ブログを始めたばかりのころ、「どうやって書けばいいの」「文章がうまくないから恥ずかしい」そんなふうに感じたことはありませんか。
大切なのは「うまく書くこと」ではなく、あなたの体験を、あなたの言葉で届けることなのです。
誰かの心にそっと寄り添うようなことができる体験談や、ほんの少し前を歩く先輩の声として経験を話すことで、読者の背中をそっと押すことができるのがブログを書くということです。
自分が悩んだこと、迷ったこと、うまくいかなかったことなどの中で、気づいたことを経験としてそのまま書けばいいのです。
そのことが、読者にとっては貴重な情報となるからです。
目次
ブログを書くために心がけること
ブログは「うまく書かないと読まれない」と思い込んでしまい、そのプレッシャーから手が止まってしまうことがあります。
私も最初は、「うまい文章を書きたい」「読ませる記事にしたい」そう思うあまり、長い言い回しや理屈っぽい表現ばかりになってしまっていました。
でも今は、ChatGPTに「読みやすく整えて」とお願いするだけで、驚くほどスッキリした文章に仕上げてくれます。
だから、書き手が一番大切にするべきことは、「自分の体験を、そのまま素直に伝えること」だけでいいのです。
読みやすく整えることは、ChatGPTがやさしく手伝ってくれます。
読まれるブログは、「うまく書く」より「整理されている」
読まれるブログというのは、決してうまく書かれた文章ではありません。
読者の心に届く中身があるかどうかが、いちばん大切なのです。
とはいえ、どんなに良い内容でも、まわりくどい言い回しや、語尾のばらつき、句読点の使い方などで読み疲れると、離脱されてしまうこともあります。
ChatGPTは、読みやすくわかりやすい文章に整えることは、得意中の得意だからです。
AIライティングのブログの作り方
ここからは、私が実際にやっている「AIライティングの実践方法」について紹介します。
私のAIライティングの方法
ここからは、私がどんな流れでブログを書いているのかを、AIとのやり取りも交えながらご紹介していきます。
実は、前回書いたブログでは、まさに「自分は何を書きたいのか分からない」と悩んでいた時のことをテーマにしました。
「書きたいことが見つからないとき、ChatGPTが心の声を引き出してくれた話」という記事を書いたときのことです。
まったく記事のネタが思い浮かばなく、どうしようとChatGPTに話しかけたところから始まります。
Step1:ChatGPTに話しかけることから始める
私はまず、ChatGPTに向かってこう話します。
「今日は、うまく記事が書けなかったときの気持ちをテーマにしたいと思います」
雑談のような入り方ですが、これが大切なきっかけになります。
Step2:気づきを箇条書きで整理する
ChatGPTと話す中で、自然と「何を伝えたいのか」が見えてくるのです。
それは編集会議のようなことで、テーマも何も決まっていない状態で雑談のような形で話し合います。
このようなChatGPTとの話し合いの中で、自分の気持ちを話しつつ、いくつかの記事全体の構想が見えてきました。
根底には、読者は何を知りたいかいったことを絞り込んでいきます。
Step3:何を書こうかを決める
今回は、「ブログを書くうえで、何を書けばいいか分からない時がある」というテーマを考えました。
次に、ChatGPTに「この内容に合う記事構成を考えて」と、指示を出します。
すると、こんなふうに提案してくれます。
- ブログが書けなかった自分
- テーマの種は、自分の心の中にある
- ChatGPTとの対話で見えたこと
- 読まれるブログの書き方に気づいた
テーマに沿った見出しを出してくれたので、それに従い文章を書いていきます。
Step4:記事が書き上がったら文章を読みやすく書き直す
書き上がった記事に、以下のことを指示を出すことで、ブログを整えてもらうのです。
最近では、スマホで読む人が多いことから、センテンスの短い文章が求められていて、ChatGPTは指示に従って書き直してくれます。
1文を短く40文字以内
1段落は4〜5行まで
段落ごとに見出しをつける
行間をしっかり空ける
大事な言葉は太字や記号で強調する
箇条書きを活用する
内容を詰め込みすぎず、読ませるというより見るような文章を意識する
Step5:仕上げられた記事を読みながら推敲する
ChatGPTに手伝ってもらい記事が出来上がったら、自分が読んで推敲を重ねます。
同時に、ChatGPTにブログ全体のトーンをチェックしてもらいます。
以下のように、ChatGPTへのプロンプトで指示を出します。
「文章が回りくどくないかチェックして」
「読みやすい構成になっているか確認して」
「専門用語など使わないで、読みやすいように整っているか確認して」
「結びの言葉は共感を呼ぶ内容になってるか確認して」
仕上げを評価してもらう
ブログ記事が出来上がったら、全体をChatGPTに読んでもらい「評価してほしい」と指示を出します。
そうすると、誤字脱字や言い回しなど、不自然なところを洗い出してくれます。
指摘されたところを書き直して、次に題名を考えてもらいます。
タイトルは、最初よりも最後に整える方が効果的なのは、本文とのズレがなくなるからです。
メタディスクリプションは、記事全体を要約した短文として、100〜120字で考えてもらいます。
ついでに、SNS用の文章も考えてもらいましょう。
私は、このような流れでAI と一緒にブログを書いています。
最後にもう一度、私のAIライティングの流れをまとめます
AIライティングとは、AIにすべて書いてもらうことではありません。
私にとってChatGPTは、記事作成の相談相手であり、心強いアシスタントです。
- ChatGPTに「書きたいこと」を話しかける
- 見出しや構成を考えてもらう
- 思いついたことを自由に書き出す
- 読みやすく整えるのはChatGPTにお願い
- 最後に「読者に届くか」をチェックしてもらう
この流れで、私は伝わる文章を、毎日のように書いています。
私にとって、ChatGPTがいるからこそ、気負わずに自分の気持ちを形にすることができています。
あなたも、ChatGPTでブログを書いてみませんか。
【付録」私のAIライティングのテンプレート
AIライティング執筆テンプレート
① 書きたいテーマ・気づきを言葉にする(素直な気持ちで)
今日感じたことは「うまく書こうとすると、逆に伝わらないことがある」ということです。
ここから、読者に伝えたい気づきや体験を整理したいです。
➡ ChatGPTにそのまま話す:「こんなことをテーマに記事を書きたいんだけど、どう思う」
② 伝えたいことを箇条書きで出して整理する
・何に悩んだのか(体験)
・どんな気づきがあったか
・読者にどんなメッセージを届けたいか
➡ ChatGPTに話す:「この3つを軸にして構成を考えてもらえますか」
③ 見出し構成を一緒に作る(3~5見出し)
H1:テーマに気づいたきっかけ
H2:過去の苦しかった書き方
H2:ChatGPTとの対話からの変化
H2:伝わるために気をつけていること
H2:読者に伝えたいこと・結び
➡ ChatGPTに話す:「この内容に合う見出し構成を、短く・やさしく提案して」
④ 各見出しごとに、短く・端的に伝える(1ブロック=5行以内)
✔ 1文は40文字以内
✔ 1段落は3~4行
✔ 行間をしっかり空ける
✔ 大事な言葉は強調(太字や記号)
✔ 箇条書きを活用する
➡ ChatGPTに指示:「この段落をもっと短くしてください」「箇条書きにしてください」
⑤ 書き終えたらChatGPTに全体チェックを依頼する
聞く内容の例:・文章が回りくどくないかチェックして
・読みやすい構成になっている
・スマホでも読みやすいように整ってるか確認して
・結びの言葉は共感を呼ぶ内容になってる
⑥ 最後に「読後感」と「読者の背中を押す言葉」を入れる
あなたの気づきは、誰かの希望になります。
書けない時期があっても、きっとまた書きたくなります。
➡ ChatGPTに相談:「この記事の締めくくりとして、やさしい応援の言葉を入れてください」
まとめ:AIライティング7つのステップ
1. 自分の気持ちや体験をChatGPTに話す
2. ChatGPTがまとめた文章を見て整える
3. 「もっと短く」「読みやすく」など指示を出す
4. 段落・センテンス・行間をスマホ読み仕様に整える
5. 必要に応じて箇条書きに
6. 最後にChatGPTに「評価」をお願いする
7. 最後の手直しは、自分の気持ちを優先して整える